借地借家法(建物)(全27問中20問目)
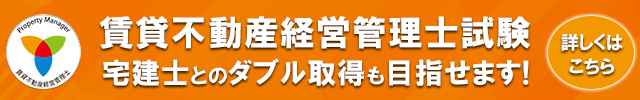
No.20
借地借家法第38条の定期建物賃貸借(以下この問において「定期建物賃貸借」という。)と同法第40条の一時使用目的の建物の賃貸借(以下この問において「一時使用賃貸借」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。平成19年試験 問14
- 定期建物賃貸借契約は書面又は電磁的記録によって契約を締結しなければ有効とはならないが、一時使用賃貸借契約は口頭で契約しても有効となる。
- 定期建物賃貸借契約は契約期間を1年以上とすることができるが、一時使用賃貸借契約は契約期間を1年以上とすることができない。
- 定期建物賃貸借契約は契約期間中は賃借人から中途解約を申し入れることはできないが、一時使用賃貸借契約は契約期間中はいつでも賃借人から中途解約を申し入れることができる。
- 賃借人が賃借権の登記もなく建物の引渡しも受けていないうちに建物が売却されて所有者が変更すると、定期建物賃貸借契約の借主は賃借権を所有者に主張できないが、一時使用賃貸借の借主は賃借権を所有者に主張できる。
広告
正解 1
問題難易度
肢160.1%
肢213.3%
肢317.0%
肢49.6%
肢213.3%
肢317.0%
肢49.6%
分野
科目:1 - 権利関係細目:15 - 借地借家法(建物)
解説
- [正しい]。定期建物賃貸借は、公正証書による等書面又は電磁的記録でしなければなりません。公正証書による等書面とは、公正証書などの書面という意味です(借地借家法38条1項)。
一時使用賃貸借には民法の賃貸借の規定が適用されるので、契約方式は問われません。口頭での契約も可能です(借地借家法40条)。期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。
この章の規定は、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、適用しない。
- 誤り。定期建物賃貸借には存続期間の上限も下限もありません(借地借家法29条2項)。
一時使用賃貸借の場合は民法の規定に従い最長が50年とされていますが、最短期間の制限はありません(民法604条1項)。民法第六百四条の規定は、建物の賃貸借については、適用しない
賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
- 誤り。床面積200㎡未満の居住用建物を目的とする定期建物賃貸借では、転勤、療養その他のやむを得ない事情により、建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となった賃借人は、中途解約の申入れをすることができます(借地借家法38条7項)。
一時使用賃貸借の場合は、民法の賃貸借の規定が適用されるため以下のようになります。- 期間を定めなかったとき(民法617条)
- いつでも解約を申し出ることができる
- 期間を定めた場合(民法618条)
- 期間内に解約をする権利を留保したときは解約できる
第一項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が二百平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から一月を経過することによって終了する。
本件契約が借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約である場合、Aの中途解約を禁止する特約があっても、やむを得ない事情によって甲建物を自己の生活の本拠として使用することが困難になったときは、Aは本件契約の解約の申入れをすることができる。(R4-12-3)本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約である場合、Aは、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情があれば、Bに対し、解約を申し入れ、申入れの日から1月を経過することによって、本件契約を終了させることができる。(R2⑩-12-3)AB間の賃貸借契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借で、契約の更新がない旨を定めた場合には、当該契約の期間中、Bから中途解約を申し入れることはできない。(H30-12-2)居住の用に供する建物に係る定期建物賃貸借契約においては、転勤、療養その他のやむを得ない事情により、賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、床面積の規模にかかわりなく、賃借人は同契約の有効な解約の申入れをすることができる。(H20-14-4) - 誤り。定期建物賃貸借では、賃借権の登記または建物の引渡しにより賃借権を第三者に対抗することができます(借地借家法31条)。しかし、本肢では引渡し前に建物が売却されているので、借主は新所有者に賃借権を対抗することはできません。
一時使用賃貸借の場合は、借地借家法の適用がないため、引渡しによる対抗はできず賃借権の登記が必要となります(民法605条)。よって、借主は新所有者に賃借権を対抗することはできません。建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。
不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。
本件契約が借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約であるか否かにかかわらず、Aは、甲建物の引渡しを受けてから1年後に甲建物をBから購入したCに対して、賃借人であることを主張できる。(R4-12-2)本件契約期間中にBが甲建物をCに売却した場合、Aは甲建物に賃借権の登記をしていなくても、Cに対して甲建物の賃借権があることを主張することができる。(H22-12-1)Aが甲建物をDに売却した場合、甲建物の引渡しを受けて甲建物で居住しているBはDに対して賃借権を主張できるのに対し、Cは甲建物の引き渡しを受けて甲建物に居住していてもDに対して使用借権を主張することができない。(H21-12-3)Aが借入金の返済のために甲建物をFに任意に売却してFが新たな所有者となった場合であっても、Cは、FはAC間の賃貸借契約を承継したとして、Fに対して甲建物を賃借する権利があると主張することができる。(H20-4-4)借地権の期間満了に伴い、Bが建物買取請求権を適法に行使した場合、Aは、建物の賃貸借契約を建物の新たな所有者Cに対抗できる。(H18-14-2)Aが、建物に自ら居住せず、Bの承諾を得て第三者に転貸し、居住させているときは、Aは、Bからその建物を買い受けた者に対し、賃借権を対抗することができない。(H12-12-1)
広告
広告